TL;DR(最初にざっくり)
LLMは「大量の文章から次に来そうな言葉を高精度で予測するエンジン」。
仕組みの要はトークン(言葉のかけら)とTransformer(注意機構)。
上手に使うコツは良い指示(プロンプト)・外部知識との連携(RAG)・安全配慮です。
1. LLMってなに?一言でいうと
LLM(Large Language Model)は、文章を読み書きできるAIモデル。
たくさんの文章を学び、「次に続く言葉(トークン)」の確率を予測します。
- 例:「今日は空がとても…」→ きれい / 青い / 明るい … の中から最も自然な続き方を選ぶ
- これを高速に繰り返すと、説明文も、要約も、コードも、メールも書けます。
ポイント:LLMは“事実データベース”というより言葉の予測器。だからこそ根拠確認が大切です。
2. どうやって学ぶの?(データ・トークン・パラメータ)
学習データ
- 書籍、Webページ、論文、コード、対話データなど、大量のテキスト。
- モデルは「この文脈ではこのトークンが来やすい」というパターンを学習します。
トークンって?
- 文章をそのままではなく、細かな単位(トークン)に分解して扱います。
英語だと単語の一部、日本語だと文字やサブワードなど、モデルごとに分割の仕方が異なります。 - 「トークン数」は入力の長さや料金、応答の上限に関わる重要な指標です。
パラメータ(重み)
- モデルが持つ“設定つまみ”の数。
- 学習とは、正解に近づくようにつまみを微調整し続けること(最適化)。
3. コア技術「Transformer」とは
LLMの心臓部がTransformer。カギは自己注意(Self-Attention)です。
「注意」の直感
文の中でどの部分が今の単語に関係深いかを重み付けして理解します。
文: 「明日 雨 が 降ったら、 傘 を 持っていこう」
▲――――関係――――△
「降ったら」⇔「雨」⇔「傘」 の関連に強く“注意”
- 長い文脈でも関連箇所をダイレクトに参照できるのが強み。
- これを多層に重ねることで、抽象的な関係も学習できます。
自己回帰生成
- 1語(トークン)ずつ予測→付け足す→また予測…を繰り返し、文章を生成します。
4. 使うときのポイント(推論・温度・長さ・役割)
推論(inference)
学習済みモデルに入力(プロンプト)を渡し、出力を得るフェーズ。
代表的な設定
- 温度(temperature):0に近いほど堅実、高いほど多様。
- 確率質量(top‑p):高確率の候補からどこまで広げて選ぶか。
- 最大トークン数:返答の長さ上限。長すぎると中断されることも。
- 役割(system / user / assistant):
- system:全体方針(文体、守るルール)
- user:あなたの依頼
- assistant:モデルの返答
テンプレ(基本形)
- 目的(何を出したいか)
- 制約(語数・形式・対象読者)
- 手順(箇条書き)
- 出力フォーマット(例:表・JSON・箇条書き)
- 例示(良い例・悪い例)
5. LLMの「賢さ」の正体(知識と推論、埋め込み)
暗黙知(統計的パターン)と推論
- LLMは学習時に多くの知識パターンを圧縮。
- 一方で最新事情や数値の厳密計算は苦手なことも(外部ツール併用が有効)。
埋め込み(Embedding)
- 文章や単語をベクトル(数列)で表す技術。
- 意味が近いほどベクトルも近いので、検索やクラスタリングに使えます。
- 例:FAQの質問文を埋め込み→ベクトルDBに保存→ユーザーの質問に最も近いQ&Aを即時提示。
6. 弱点と注意点
- ハルシネーション(もっともらしい誤情報)
- 根拠が必要な回答には出典の提示や確認質問を求める。
- コンテキスト窓(記憶の作業領域)
- 入力が長すぎると古い部分が参照しにくい。要約・分割が有効。
- 偏り(バイアス)
- 学習データの偏りが出力に反映される可能性。表現や判断の公平性に配慮。
- プライバシー・機密
- 個人情報や未公開情報の取り扱いに注意(社内運用ルールを整備)。
- 厳密計算・最新情報
- 計算はツール、最新情報は検索やデータベースと分業すると精度が上がります。
7. もっと賢くする方法:RAG・ファインチューニング・ツール連携
RAG(検索拡張生成)
- 質問を受け取る
- 社内文書やWebから関連文書を検索
- 見つかった文書をプロンプトに同梱
- 根拠つきの回答を生成
向いている用途:最新マニュアル、製品仕様、社内ナレッジの参照
ファインチューニング(追加学習)
- 特定の文体・業務手順・専門タスクに合わせて振る舞いを微調整。
- 大量の高品質データがあるときに効果的。ない場合はプロンプト設計+RAGから。
関数/ツール呼び出し(関数実行・API連携)
- LLMが「いまは検索が必要」と判断→外部ツールに問い合わせ→結果を使って再回答。
- 例:計算、データベース照会、在庫確認、分析APIなど。
8. コストと性能の考え方
- モデルサイズ:大きいほど一般に高性能だが、費用・遅延が増える。
- 課金のイメージ:多くのサービスはトークン課金(入出力トークンに応じて料金)。
- 実務運用:
- 企画・要約などは汎用大モデル
- 高頻度の定型処理は軽量モデルやファインチューニング
- 知識参照はRAG+ベクトルDB
9. すぐ使えるプロンプト例8選
- 要約(役員向け・短く)
- 「次の文章を3行で要約。読者は経営層。結論→理由→数字の順で。」
- 文体変換(丁寧語)
- 「次の文を社外メール向けの丁寧語に書き換えて。」
- 情報抽出(構造化)
- 「テキストから会社名・部署名・担当者・メールを抽出し、JSONで返して。」
- ブレスト(多様性重視)
- 「新商品のキャッチコピーを温度高めで20案。短く・比喩あり。」
- 手順書化
- 「この作業ログを誰でも再現できる手順書に。前提・必要物・手順・チェック項目で。」
- 表作成(仕様比較)
- 「AとBの違いを表で。用途/長所/短所/コスト/導入難度の列を作って。」
- 正規表現ヘルプ
- 「次の条件を満たす正規表現を作って。条件:… 例と非例も提示して。」
- (ウェブ解析向け)計測設計の骨子
- 「LPのKPI/イベント/タグ/トリガー/命名規則を表で提案。初心者でも実装可能な前提で。」
10. よくある質問(FAQ)
Q1. LLMは“知っている”の?
A. 「覚えている」というより、言語パターンを圧縮しているイメージ。最新の事実確認は検索やデータと併用を。
Q2. なぜ間違うの?
A. 目的は「もっともらしさの最大化」。自信ありげでも誤りが混じることがあります(ハルシネーション)。
Q3. 日本語は苦手?
A. モデルと学習データ次第。プロンプトを日本語で明確にすれば十分実用的な出力が期待できます。
Q4. どのくらい長い文を扱える?
A. コンテキスト上限があります。長文は要約・分割・重要箇所の抜粋が有効。
Q5. セキュリティは?
A. 個人情報・機密情報の取り扱いルールを明確に。オンプレ/専用環境やマスキングも検討。
11. 用語ミニ辞典
- LLM:大規模言語モデル。次のトークンを予測するAI。
- トークン:文字や単語のかけら。入力/出力の基本単位。
- パラメータ:モデルの重み。学習で最適化される。
- Transformer / Self-Attention:文中のどこに注目すべきか学ぶ仕組み。
- 推論(Inference):プロンプトから回答を生成する工程。
- 温度 / top‑p:出力の多様性を制御する設定。
- コンテキスト窓:一度に扱えるトークン数の上限。
- 埋め込み(Embedding):文章を意味ベクトル化する技術。
- RAG:検索結果など外部知識を取り込み根拠付き回答を出す方式。
- ファインチューニング:特定用途向けに振る舞いを追加学習で調整。
12. 導入チェックリスト
- 目的は何か(要約/回答/分析支援/自動化)
- 取り扱うデータの機密レベルは?ルールは整備済み?
- プロンプトテンプレは整っている?(目的・制約・形式)
- 必要な最新知識はRAGで補える?ベクトルDBの準備は?
- 評価方法は?(人手評価の観点・自動指標・ガードレール)
- コスト/遅延の要件(どのモデル・どの頻度)
- 将来の保守・運用(ログ、バージョン管理、改善サイクル)
まとめ
LLMは「言葉の予測」を極めたエンジンです。プロンプト設計で振る舞いを整え、RAGやツール連携で現実世界のデータと結びつければ、企画・文書化・サポート・分析・自動化まで幅広く活用できます。
一方で、ハルシネーションやバイアス、機密性への配慮は必須。
小さく試し、目的に合わせて設計→評価→改善のループを回すことが成功の近道です。
付録:そのまま使える基本テンプレ
# 役割
あなたは[役割]です。出力は日本語。
# 目的
[何を達成したいか]
# 制約
- 文字数/見出し/対象読者/トーン
- 禁止事項(推測で確定表現にしない 等)
# 手順
1) ...
2) ...
# 出力形式
- 見出し構造 or 表 or JSON など
# 参考
- 必要ならサンプル・定義・評価観点
必要であれば、実務シナリオ(例:社内FAQのRAG設計、レポート自動要約、GTM/GA4の手順書化)にあわせた具体的な設計図・サンプルも作成します。
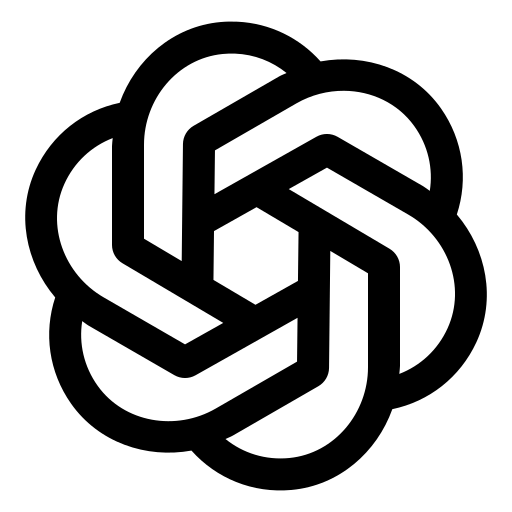

コメント